
濱田庸子研究会

褒めることとコンプレックスの関係について
―総合政策学部 瀬戸みさ乃
コンプレックスはいつ、どこで生まれるのか。乗り越えるためにはどうすれば良いのか。それを「褒める」という観点から考えてます。また、それぞれの褒められて一番うれしい部分はどのように決まるのでしょうか。
ノートを設置し、アンケート調査を実施します。性別・年齢に加え、自分が褒められて最も嬉しい部分を3つ書いていただき、また可能な範囲でコンプレックスも書いていただく、簡単な調査です。ぜひ、ご協力くださいますと幸いです。

「精神障害を理解する」とは?
―総合政策学部 田中初海
どんな病気でも、治療するにあたり病気を理解することが治療の第一歩となる。
それが目に見える病気であれば、レントゲン写真等を観ながら、家族は患者の病気の症状、薬の副作用、生活上気をつけなければいけないことを理解したうえで患者と接する。
では目に見えない精神疾患の治療においてはどうだろうか。
今回の展示では精神障害に関する偏見を通じて精神障害を理解することとはどういうことなのか探っていく。

容姿についての美醜の心理
―総合政策学部 金田奈々
私たちの周りにはメディアで目にするモデルを始め「魅力的とされるイメージ」が溢れていますが、どのような容姿を理想とし美しいと思うのか、個人が持つ美醜の感覚や基準は様々です。
そこで身体醜形障害やボディイメージをもとに、それらがどのように形成されるのかを探るとともに、心理的要因との関係を考察して行きたいと思います。
美醜へのこだわりと自己肯定感との関係や、幼少期に過ごした環境との関係など、美醜の心理は何をもって変化し形作られていくのか研究しました。

お茶とストレスコーピング
―総合政策学部 志鎌奈津美
家庭の在り方や、お茶の間文化の変化により、お茶が生産量・消費量共に減少してきています。そこで、お茶で心理的に解決していける問題を探し、お茶の新しい活用方法としてストレスコーピングを提案すべく、ストレスに焦点を絞り、お茶と心の関係を研究しています。最終的には新商品、新事業を提案していきます。
具体的に、お茶を飲んでもらいどう感じたか等のアンケートやインタビューを行います。また、香りや色によってどんな印象を受けるか等も調査していきます。この研究で多くの人にお茶の魅力を知ってもらいたいと思います。

高齢者の孤独について
―環境情報学部 大城華莉絵
この研究では、「高齢者の孤独」に関する認識が、高齢者が身近にいる場合とそうでない場合でない場合でどう違うのかを検討します。また、高齢者とどのように関わる環境や関係がある時に、関心が高くなるのかなどの関連性も探りたいと思っています。

ダイエットとストレスマネジメント
―環境情報学部 高橋佳奈
多くの人が経験し、悩まされているダイエットですが、いつも上手くいかないと感じている人も多いのではないでしょうか?
この研究では、
・どのようなダイエットが心に負担にならずに続けられるか?
・どのようなダイエットが心の負担になるのか?
・ストレスマネジメントをどのように行っていくと良いのか?
という視点を中心として、ダイエットとストレスの関係性や、ダイエットとうまく付き合っていく方法などについて考えていきます。

森さち子研究会

意味ネットワークを活用した語彙指導における言語間の気付きに関する研究
~パイロット研究として~
―総合政策学部 飯島尚憲
私は, 英語教育における語彙の指導について研究を行っています. 近年, 学習指導要領の改定に伴い, 中学・高校で扱う英単語の数が倍増しました. 現場の先生方も生徒に市販の単語集を渡してテストを行うという形式から, 授業中に単語の解説を行うことで単語を覚えてもらえるような授業を行うという工夫が要求されています. 本研究では,「意味ネットワーク」という概念から語彙指導のあり方を模索しました.「夏」という日本語, そして同じ意味の英単語「summer」から連想する語を実験参加者に自由に記述してもらい, 書かれたものについて特定の語彙リストにて解析をしました. その解析データをもとに考察を行い, 教育実践へ何ができるかということを模索しました.

『モテる』同性、異性にとって魅力的な人とは
―総合政策学部 大島圭裕
「モテる」人。この言葉を聞いた時に、どんな人が想起されますか。誰に対しても、相手の懐に入り、魅力的だと思わせる人はあなたの身の回りにいると考えます。本研究では、男女問わず魅力的だと思われる人には、いかなる特徴があるのか、心理学という視点から分析していきます。

他者から見える自分の姿、考えたことありますか?
―総合政策学部 末松大知
私は、相手が自分に抱く印象と、自分が考える「相手が自分についてどのような印象を抱いているのか」これら2つにどのような相違があるのかについて研究しています。この研究では、当事者研究の形をとっており、自分をしっかりと分析することによって、将来人間関係が広がっていく中で活かしていきたいと考えています。ORFの中で、多くの方とたくさん話をしたいと考えていますので、当日はよろしくお願いいたします。

女子学生の結婚願望と心理的居場所感希求の連関およびそれらが精神的健康に与える影響
―環境情報学部 猪尾風花
結婚という選択肢の肯定、あるいは、それに執着する必要がないことの示唆を目指し、社会に出る以前の女性が抱く “結婚したい” という意識の奥に何が隠れているのか、彼女らにとって結婚を夢見ることがどのような意味を持つのかについて探ろうとしている。また、結婚願望および心理的居場所感希求が精神的健康に及ぼす影響を調査する。
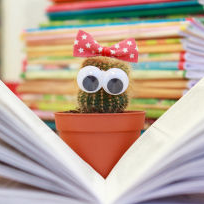
育ってきた教育方針・性格ごとの最も有効な劣等感への対処法
―環境情報学部 佐伯拓海
劣等感を抱くことは多くの人に共通する点であると考える。私もその多くの中の1人である。 劣等感に対する、対処法。対処法を育ってきた教育方針や、その人の性格、家族構成、劣等感の種類により分類し、その人にとって最も良い対処法、テンプレートを私の研究では調査する。

「よりどころ」を考える
―環境情報学部 相原香菜子
私は「よりどころ」について研究をしています。 人生を送るにあたって、支えや頼りとなる「よりどころ」は人それぞれです。 人がどのようにして「よりどころ」を獲得し、影響を受けていくのかをインタビューを通して分析していきます。また、インタビューを通して『自分の「よりどころ」について自覚的であることはストレスコーピングにつながる』という自身の仮説の是非を考察します。最終的には、エッセイ形式の読み物としてまとめる予定です。

「パリジェンヌ」「ニューヨーカー」への憧れから見る、女子大学生のストレスについて
―総合政策学部 小林里佳
今、20代・30代の女性を中心に「パリジェンヌ」や「ニューヨーカー」などの外国人女性の生き方に関する書籍が売れています。 私は、どうしてこのような本が今若い女性を中心に人気となっているのかということに疑問を持ち、「パリジェンヌ」や「ニューヨーカー」の自分軸を持った生き方に憧れるのは、そのように生きられない現状の自分に不満を持っているからなのではないかと考えました。そこで、自分軸を持つことと女子大生が抱えるストレスについての研究をしています。

サイコスペース(大学院プロジェクト)

知能の発達と知能検査
―政策・メディア研究科 髙橋麻李衣
私たちヒトの知的能力(知能)は、身体と同じように絶えず発達を続けていて、年齢によって得意な能力も徐々に変化していきます。本研究ではそうした知能の発達の過程を踏まえた上で、ヒトの知能を測定するための心理検査である「知能検査」を扱います。
本展示では、日本国内で用いられてきた知能検査と海外で開発された知能検査の種類や歴史を比較し、今後日本国内でも必要になると考えられる知能検査の検討過程などを紹介しています。
*本研究は前川ヒトづくり財団の助成を受けたものです。

おじいちゃん いつ頃死ぬのかしら
―政策・メディア研究科 伊藤輝夫
日本人の平均寿命が長くなって久しい今日、高齢者とその家族の隔たりが漠然と存在することを感じたことはありませんか?
介護をする側と受ける側の状況や心理的な隔たりに焦点を当て、高齢者の老後に関する研究を行っています。